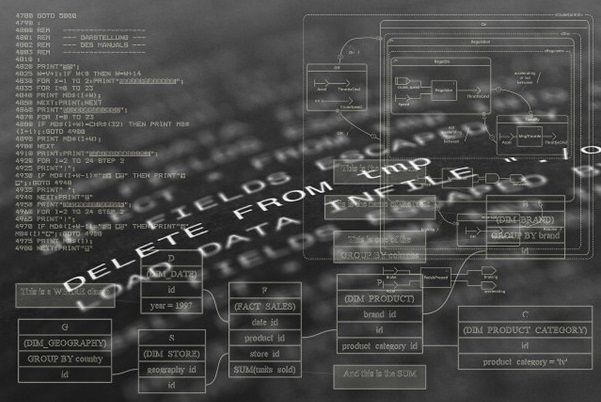CRA SBOM対応|全体像と要件を条項ごとに分かりやすく解説
CRAの重要な要素の一つとして「SBOM対応」があります。SBOMとは「Software Bill of Materials」の略で、ソフトウェアを構成している部品と部品同士の依存関係をリスト化した「ソフトウェア部品表」です。(※)
この記事では、CRAにおけるSBOMの位置付けや、CRA条項ごとの対応関係を整理し、実務で押さえるポイントを分かりやすく解説します。具体的には、SBOMの作成・運用・提供体制の構築に加え、社内教育やベンダー連携などの紹介です。
※出典:経済産業省「ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引」
CRAがSBOMを求める理由と背景を理解する
CRA(サイバーレジリエンス法)では、SBOMの提出や管理が強く求められています。ここでは、その背景や法的要請の構造について整理していきます。
なぜ今SBOMが注目されているのか
サイバー攻撃の多様化とサプライチェーンの複雑化により、製品に含まれるソフトウェアの透明性が国際的に求められています。特に2021年に米国で発令された「大統領令14028」や「NTIAのSBOMガイドライン」以降、SBOMはセキュリティ対策の「見える化ツール」として注目されている状況です。
「大統領令14028」とは、米国のサイバーセキュリティの改善に関するもので、「NTIAのSBOMガイドライン」とは、NTIA(米国商務省電気通信情報局)が発表したSBOMの作成と利用を促進するための方針になります。(※)
CRAでは「悪用可能な脆弱性が含まれていないこと」が要件となっており、製品に使用される全コンポーネントを正確に把握するためにSBOMの整備が不可欠とされています。(※)
※出典:経済産業省「ソフトウェアに向けたSBOMの導入に関する手引き ver2.0」(P17)
European Union「EUR-Lex(附属書Ⅰ-必須のサイバーセキュリティ要件)」
CRAが求めるソフトウェア構成の可視化とは
CRA 第31条では、製品のセキュリティ特性や構成情報を技術文書として提示することが求められています。(※)
SBOMは「構成情報の根拠資料」として活用され、各ソフトウェアコンポーネントの名前、バージョン、提供元、ライセンス情報などを明記する形です。
また第13条では、アップデート提供に関して、改変された構成情報の明示も義務付けられており、SBOMの定期更新が必要になります。(※)
※出典:CYBER RESILIENCE ACT「サイバーレジリエンス法」(第13条、第31条)
欧米の法制度との「共通点」「相違点」
CRAの要件は、米国の「大統領令14028」やEUの「NIS2指令」などと類似性があります。「大統領令14028」とは、米国のサイバーセキュリティの改善に関するもので、「NIS2指令」とは、EUが施行したサイバーセキュリティ対策強化の指令です。(※)
例えば、CRA 第13条の「脆弱性への対応責任」は、これらの欧米の法制度と考え方が共通しています。ただし欧米の法制度はガイドラインベースなのに対して、CRAは罰則付きの義務規定である点が異なっています。
※出典:NIS2 Directive「NIS2:欧州史上最も広範なサイバーセキュリティ指令」
CYBER RESILIENCE ACT「サイバーレジリエンス法」(第13条)
CRA条文とSBOM対応項目のマッピング
CRAではSBOMに直接言及されていないものの、多くの条文がSBOMによって対応可能となっています。ここでは、各条文が求めている情報と該当するSBOM項目を整理します。
SBOMに関係する主要条文の一覧と読み解き方
CRAの条文と、対応するSBOM項目を下表にまとめました。条文の背景を理解した上で、SBOMの各情報項目と関連付けることが重要です。
| CRA条文 | 条文の要求内容 | 対応するSBOM要素 |
| 基本的なセキュリティ要件(第13条) | 製品に既知の脆弱性を含まないこと | ソフトウェア名、バージョン、ハッシュ、依存関係 |
| 製品情報の提供(第14条) | 利用者が製品の構成情報を確認できる状態にすること | ソフトウェア名、提供元、ライセンス情報 |
| セキュリティアップデート(第13条) | 更新履歴・更新理由・適用状況を文書化すること | 更新履歴、差分情報、アップデート対象 |
| 技術文書の提出(第31条) | 評価機関への構成情報などを文書で提出すること | 構成情報、署名付きの形式ファイル |
※出典:CYBER RESILIENCE ACT「サイバーレジリエンス法」(第13条、第14条、第31条)
条文ごとに求められるSBOM項目の具体例
CRAでは「既知の脆弱性を含まない」ことが求められています。これはSBOMに記載されたコンポーネントのバージョン情報と、脆弱性データベースを照合する運用が対応している状況です。またCRAで「製品情報の提供」が求められていますが、SBOMの項目としてソフトウェア名、バージョン、提供元、ライセンスなどを利用者に提示できる形で保持しておくことで要求を満たすことが可能です。
このように、各条文に対してSBOMにどの情報を含めればよいのかを明確にすることが、CRA適合への第一歩となります。
評価機関への提出を想定した文書の整備ポイント
CRAでは、適合性評価を行う際に、製品構成や更新体制の文書を評価機関へ提出する必要があります。このとき、SBOMを作成していれば構成情報の証拠資料として活用が可能です。
求められているのは、「SPDX」や「CycloneDX」といった標準形式で整備されたSBOMで、記載内容にはソフトウェア名、バージョン、ハッシュ、依存関係、ライセンスなどを含めます。
さらに、差分の記録や更新履歴といった動的情報もSBOMに入れることで、審査時の信頼性が向上します。評価機関からの指摘リスクを減らすには、提出前にSBOMの整合性チェックを行うことが重要です。
CRAに準拠したSBOMを作成・更新する実務プロセス
CRA対応に求められるSBOMは、「一度作成すれば終わり」ではありません。作成後も更新していく必要があります。そのため、更新を前提とした体制の構築が必要です。ここでは、SBOMに含めるべき情報、社内運用ルール、体制構築について解説します。
SBOMに含めるべき情報とフォーマット
CRAで要求されるSBOMには、標準化された情報の記載が必要となります。含めるべき主な要素は次のとおりです。
- ソフトウェア名とバージョン
- ライセンス種別と提供元
- 暗号学的ハッシュ(SHA-256など)(※)
- 各コンポーネントの依存関係
これらを正確に記録、共有するため、SPDXやCycloneDXといった標準フォーマットの使用が推奨されます。SPDXはライセンス情報との親和性が高く、CycloneDXは脆弱性管理との統合がしやすい利点があります。製品リスクの管理目的でSBOMを提出する場合は、機械可読性があるこれらのフォーマットが効果的です。
※出典:IT用語辞典「SHA-256」
社内運用ルールの策定とツールの選び方
SBOMは作成して終わりではなく、更新と活用を前提にした社内ルールが必要です。例えば次のような運用ルールが有効といえます。
- 各開発フェーズ内にSBOM生成を組み込む
- ソフトウェア統合時やリリース時に最新SBOMとの相違チェックを行う
- リリースドキュメントにSBOMを添付するルールを設ける
SBOMを自動で生成したり、管理したりできるツールが公開されています。(※)
ツールを選ぶ際は、社内システムとの親和性、生成フォーマット、更新対応のしやすさなどを確認することが重要です。
※出典:経済産業省「ソフトウェアに向けたSBOMの導入に関する手引き ver2.0」(10.3.2章)
SBOMを第三者評価や出荷に活用する体制
CRA 第31条で求められているのは、適合性評価のための技術文書の整備です。SBOMはその中核を担う資料として利用されています。例えば次のような用途です。
- 評価機関への構成情報の提示
- 出荷時に添付するソフトウェアの構成資料
- ソフトウェアの更新内容を示す資料
SBOMは電子データで管理し、改ざん防止や履歴保持ができる保管場所が必要です。クラウドストレージや内部レジストリを活用し、常に最新版を維持できる体制を整備してください。SPDXファイルに署名を付けて、証跡として活用する方法も有効です。
※出典:CYBER RESILIENCE ACT「サイバーレジリエンス法」(第13条)
サプライチェーンと連携したSBOM提供の実務対応
CRAに準拠するためには、自社内だけでなくサプライチェーン全体でSBOM対応が必要です。ここでは、ベンダー契約の工夫、形式統一の手法、社内教育のポイントなどを解説します。
外部ベンダーとのSBOM提供契約に盛り込むべき条項
SBOMの整合性と信頼性を確保するには、外部ベンダーとの契約書に具体的な条項を明記する必要があります。例えば、次のような要素です。
| 要素 | 内容 |
| 提供義務 | 製品に含まれるすべてのコンポーネントをSBOMに記載して提出する |
| 提出形式 | SPDXまたはCycloneDXなど、指定フォーマットで作成する |
| 更新義務 | バージョン変更やセキュリティパッチ適用時にSBOMの更新を義務化 |
また、虚偽報告への責任範囲や、SBOMの監査受け入れに関する条文を明文化しておくのも有効な方法です。
フォーマットの違いを吸収する統一運用の仕組み
複数のベンダーから受け取るSBOMは、フォーマットや記載の粒度に差が出やすいため、社内で標準化する仕組みが必要です。例えば次のような仕組みが有効といえます。
- CycloneDXとSPDXを変換できるOSSツールを活用する
- 各フィールドの必須項目がルールどおりかどうかをチェックする「バリデーションスクリプト」を導入する
- API連携で社内SBOMへ自動インポートする仕組みを構築する
受け取ったSBOMをそのまま保管するのではなく、変換や補完をするなどして統一データベース化する仕組みが必要です。
開発チーム・関係者向け教育をどう実施するか
SBOM運用は、IT部門だけでは完結しません。開発、調達、品質保証など、他部門の理解と連携が不可欠です。また評価機関からの指摘に備えて、SBOMの更新・承認プロセスを理解しておく必要もあるでしょう。例えば、次のような関係者向けの教育も有効な手段です。
- CRAとSBOMの関係を図解で説明したマニュアルを社内に配布
- SBOM作成の社内教育を実施
- 更新時期や提出基準をまとめたガイドラインの整備
継続的な教育と、属人化しない体制の構築が、信頼性の向上にもつながります。
SBOMが企業のセキュリティと経営に与える本当の効果
SBOMは法令対応だけでなく、事業リスクの低減や経営判断の支援にも関係します。ここでは、実務・法務・経営の観点から、具体的な導入効果を説明します。
脆弱性対応スピードの向上と実際の事例
SBOMを作成することで、脆弱性の影響範囲を即座に特定できます。例えば「OpenSSL」の深刻な脆弱性が報告された場合、SBOM管理を行っていれば、対象ライブラリを含む製品とバージョンを即座に洗い出すことが可能です。
修正に取り掛かるまでの工数と時間が大幅に短縮され、顧客への影響説明も素早く行うことができます。
将来の法規制・監査に備えてSBOMを活用
SBOMは、CRAへの対応だけでなく、今後予測されるほかの規制(米国大統領令14028やEU NIS2指令)などの要件にも適合できる基盤となります。(※)
例えば、監査時に「どのOSSがどの製品に使われているのか」と質問を受けた際、SBOMを提出することで即座に明示が可能です。事前にSBOM運用体制を構築しておくことは、複数の法令への横断的な対応として効果的といえます。
※出典:NIS2 Directive「NIS2:欧州史上もっとも広範なサイバーセキュリティ指令」
経営層にSBOM導入を理解・納得してもらう説明方法
経営層にSBOMの重要性を伝えるには、コストや法対応の観点だけでなく「事業継続性の確保」「ブランド信頼性の維持」といった視点で説明することが効果的です。
例えば、製品出荷停止やリコール対応が発生した場合、SBOMの有無で対応スピードや損害金額が大きく変わる可能性があります。定量的リスクとして説明資料を作成し、「攻めのセキュリティ投資」として位置付けることで、理解を得やすくなるでしょう。
まとめ
CRA(サイバーレジリエンス法)への対応において、SBOM(ソフトウエア部品表)は製品の透明性確保と脆弱性対策に欠かせない要素です。この記事では、CRAの各条文とSBOM項目の対応関係を明示しつつ、SBOMの作成・更新・提出の実務プロセスやベンダー契約、社内教育、経営層への説明方法などを解説しました。
SBOMの対応は、法令だけでなく、事業継続性とセキュリティ強化の両立につながる重要な施策といえます。
弊社が提供する「ワンストップ型セキュリティ認証取得支援サービス」では、CRAの要求に沿った現状分析から適合評価、文書化、内部体制整備まで一括で対応しています。CRA対応を進めたい企業の信頼できるパートナーとして、実効性のある支援をご提供します。
詳細資料をご希望の方は以下フォームよりメールアドレスをご登録ください。
[2025年08月06日 時点]